- 大腸がん検診を受けましょう
- 大腸がん検診(便潜血検査(2日法))について
- 横浜市大腸がん検診の対象者
- 横浜市大腸がん検診の受診方法
- 横浜市大腸がん検診の流れ
- 大腸がん検診の判定後の流れ
- 大腸がんやポリープ以外の陽性原因は?
大腸がん検診を受けましょう
 日本国内において、大腸がんはがんによる死亡原因のトップクラスであり、罹患者(病気にかかる人)は40代から増えていきます。
日本国内において、大腸がんはがんによる死亡原因のトップクラスであり、罹患者(病気にかかる人)は40代から増えていきます。
早期に発見し、治療を受けることで大腸がんによる死亡を予防できます。
早期の大腸がんには自覚症状がないことが多いため、症状が出る前に検診を受けることが大切です。
血便や腹痛、便の硬さや回数の変化など、気になる症状がある場合は、検診を受けるよりも、すぐに医師の診察を受けることをおすすめします。
すでに大腸がんや大腸ポリープの治療を受けている方は、その治療を終えてから検診を再開する時期について主治医と相談してください。また、それ以外の大腸の病気で治療を受けている方は、がん検診を必ず受けるべきか、主治医に相談してください。
横浜市大腸がん検診の対象者
| 回数 | 1年に1回 |
|---|---|
| 対象者の原因 | 男女ともに40歳以上 |
| 検査事項 | 便潜血検査(検便)、医師の問診 |
| 検査費用 | 無料 |
横浜市大腸がん検診の流れ
検便用の検査キットを使用して、便中の潜血を調べる検査です。
ご自宅で2日間の便を採取し、検査キットを提出していただきます。
大腸がん検診の判定後の流れ
結果は検診後、10日~1ヵ月後に書面にてお知らせします。
陰性
陰性(異常なし)の判定であっても、リスクがすべてなくなったわけではありません。
陰性の判定は、検査時に検体に血液が混入していなかったことを意味しますが、早期の大腸がんや大腸ポリープは出血しないこともあります。また、検査自体にも精度の限界があります。そのため、陰性の判定であっても、次回(1年後)に検診を受けることが重要です。
陽性
便潜血検査で陽性反応が出た場合は、精密検査として大腸カメラ検査を受けることをおすすめします。大腸がんは常に出血するわけではないため、1日分のみ便潜血検査で陽性が確認された場合でも精密検査が必要です。大腸がんがあっても自覚症状が現れないことは珍しくありません。「次回の検診でまた確認しよう」「症状がないから大丈夫」といった自己判断は避けてください。また、もともと痔がある方でも、出血の原因が痔によるものなのか、それとも大腸がんやポリープによるものなのかは、精密検査をしなければ判断できません。特に一度も大腸カメラ検査を受けたこと無い方は、必ず精密検査を受けるようにしましょう。
精密検査(二次検診)
 大腸検査は、一般的に大腸カメラ検査が推奨されています。
大腸検査は、一般的に大腸カメラ検査が推奨されています。
大腸検査の他の方法(カプセル内視鏡、大腸CT、大腸バリウム検査など)もありますが、小さなポリープや早期大腸がんの発見には大腸カメラ検査が有用です。
当クリニックでは、大腸カメラ検査中に発見した大腸ポリープをその場で切除する日帰り大腸ポリープ切除を行っております。ポリープの大きさや形状、リスクの高さによって、その場で切除が難しい場合には、後日入院して安全に切除する必要があります。必要に応じて高次医療機関をご紹介させていただきます。
大腸がんやポリープ以外の陽性原因は?
大腸がんやポリープ以外にも便潜血検査で陽性反応が出ることがあります。
肛門の切れ傷
便の硬さや大きさなどによる過剰な摩擦で肛門に傷ができ、少量の出血が起こることがあります。
食事
以前の方法では、血液を含む食品(赤身の肉など)の摂取や鉄剤の服用により、便潜血反応の陽性原因となっている場合もありました。しかしながら近年は免疫学的方法(ヒトヘモグロビンに対する抗体を用いて潜血の有無を検出する方法)により、食事制限の必要は無くなりました。
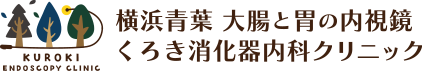



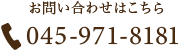


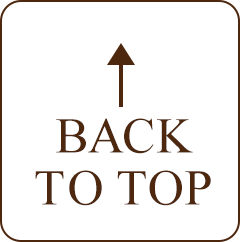

 大腸がんの検査と聞いて大腸カメラを思い浮かべる方も多いですが、大腸がん検診(便潜血検査)は、便に血液が混ざっていないかを確認する検査(いわゆる検便)です。
大腸がんの検査と聞いて大腸カメラを思い浮かべる方も多いですが、大腸がん検診(便潜血検査)は、便に血液が混ざっていないかを確認する検査(いわゆる検便)です。