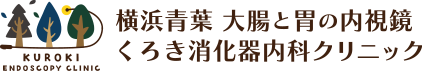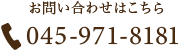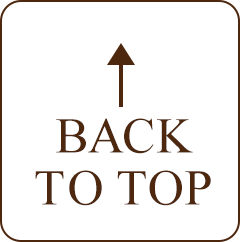潰瘍性大腸炎とは
 潰瘍性大腸炎は、大腸粘膜に炎症が起こる原因不明の慢性の炎症性腸疾患です。
潰瘍性大腸炎は、大腸粘膜に炎症が起こる原因不明の慢性の炎症性腸疾患です。
本邦では年々増加傾向にあり、20~30歳代に多い傾向がありますが、若年者から高齢者まで発症します。多くは直腸から連続性に口側(奥側)に広がっていき、炎症の範囲によって、直腸型、左側結腸炎型、全結腸炎型に分類されます。重症度は症状や血液検査などで、軽症、中等症、重症に分類されます。
潰瘍性大腸炎は厚生労働省の指定する難病ですが、適切な治療を受けて症状を抑えれば、ほぼ健康な時と変わらない生活を送ることが可能になります。
炎症性腸疾患とは
炎症性腸疾患(IBD:Inflammatory Bowel Disease)とは、主に腸管に原因不明の炎症を引き起こす慢性の疾患の総称です。
代表的な疾患として「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」があります。
潰瘍性大腸炎の症状
 潰瘍性大腸炎は、症状の悪化(再燃)と落ち着いて安定している(寛解)時期を交互に繰り返すのが特徴です。主な症状は、下痢、血便、腹痛、発熱、貧血などです。症状は炎症の部位や程度によって異なります。
潰瘍性大腸炎は、症状の悪化(再燃)と落ち着いて安定している(寛解)時期を交互に繰り返すのが特徴です。主な症状は、下痢、血便、腹痛、発熱、貧血などです。症状は炎症の部位や程度によって異なります。
また、皮膚や関節、目など腸菅以外の部位に合併症が現れることもあります。
炎症が長期にわたると、がん化する場合もあります。
潰瘍性大腸炎の原因
潰瘍性大腸炎のはっきりとした原因は未だ不明です。
免疫反応や腸内細菌、食生活の変化、環境要因、遺伝的要因なども病気の発症や再燃に関与しているといわれています。
遺伝的要因については、日本では家族内で発症する例が見られ、欧米では患者さんの約20%に近親者にIBDの方がいるという報告があります。
潰瘍性大腸炎の検査・診断
 診断は、問診により症状の経過や過去の病歴などを確認することから始まります。
診断は、問診により症状の経過や過去の病歴などを確認することから始まります。
潰瘍性大腸炎の診断では、血性下痢を生じる感染症との鑑別が必要ですので、下痢の原因となる細菌や他の感染症の鑑別診断を行います。その後、内視鏡による大腸カメラ検査で大腸内の粘膜観察や、生検を行って大腸粘膜組織の一部を採取し、病理診断を行います。このように、大腸粘膜の見た目と病理所見、感染症や他の病気を除外して潰瘍性大腸炎を診断していきます。
潰瘍性大腸炎ではありませんでした。他に症状が似ている病気は?
潰瘍性大腸炎と症状や所見が似ている病気はあります。
そのため、潰瘍性大腸炎と診断する際には、以下の病気と慎重に鑑別します。
など
潰瘍性大腸炎の治療
現在、潰瘍性大腸炎を完全に治癒させる内科的(薬物)治療法は確立されていませんが、腸の炎症を効果的に抑制し、症状をコントロールする様々な治療法が存在します。治療の目的は“早期の寛解導入”(活動性を抑える)と“長期の寛解維持”(良い状態を維持する)で、結果として患者さんのQOL(生活の質)の向上を目指します。
内科的(薬物)治療
5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤
サラゾスルファピリジンやメサラジンといったお薬があります。経口薬に加え、お尻から投与する坐剤や注腸剤があります。潰瘍性大腸炎治療の基本となるお薬で、軽症から中等症に使用されます。寛解導入だけでなく、寛解維持にも用いられます。
副腎皮質ステロイド
従来からのプレドニゾロンや、全身への影響が少ないブデソニドがあります。
経口薬や坐剤、注腸剤、注射製剤があり、中等症から重症の患者さんの寛解導入に使用されます。
血球成分除去療法
患者さんの血液を特殊なフィルターを用いて、血液中の異常活性化した白血球を除去することで炎症を抑える治療法です。ステロイド治療で効果が得られない患者さんに使用する場合があります。
免疫調節薬
アザチオプリンやタクロリムスという免疫を調整、抑制するお薬です。ステロイド中止後に症状が悪化する場合やステロイドの治療が効果的でない場合に用います。
生物学的製剤(抗TNFα拮抗薬、抗接着分子製剤、抗インターロイキン抗体薬)
バイオテクノロジー(遺伝子組換え技術や細胞培養技術)を用いて製造された薬剤で、特定の分子を標的とした治療薬です。ステロイド中止後に症状が悪化する場合やステロイドの治療が効果的でない場合に用います。主に点滴や皮下注射の治療になります。
ヤヌスキナーゼ(JAK:Janus kinase)阻害剤
ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬は炎症性サイトカインによる刺激が細胞内に伝達されるときに必要なヤヌスキナーゼという酵素を阻害するお薬です。ステロイド中止後に症状が悪化する場合やステロイドの治療が効果的でない場合に用いる、経口薬になります。
外科的(手術)治療
潰瘍性大腸炎の治療の基本は内科的治療ですが、以下のような状況では外科手術(主に大腸全摘術)が必要となることがあります:
- 内科的治療が効果を示さない場合(特に重症例)
- 大量出血が生じた場合
- 穿孔(大腸に穴があく)が起きた場合
- 大腸がんの発生またはその疑いがある場合
- 薬剤の副作用などにより内科的治療の継続が困難な場合
治療に関する重要なポイント
- 個々の患者さんの症状や状態に応じて、最適な治療法の選択
- 定期的な経過観察により、治療効果を確認します
- 必要に応じて治療法の組み合わせや変更を行います
- 副作用の管理も重要な治療の一環です
発病して長くなると大腸がんを合併するリスクが高くなってきますので、症状がなくても定期的な内視鏡(大腸カメラ)検査が必要になります。
当クリニックでは、患者さん一人一人の状態に合わせて最適な治療法を提供いたします。ご不安な点やご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。
医療費助成制度について
潰瘍性大腸炎の場合、重症度は重症・中等症・軽症の3段階に分類されます。
医療費の助成は、中等症と重症の場合に受けられます。
※軽症の方でも高額な医療を継続することが必要である場合に限り、助成を受けることができます(指定難病の軽症高額該当)。
医療費助成を受けるためには、診断書(臨床調査個人票)など必要書類を揃えて、お住まいの都道府県・指定都市窓口(保健福祉担当課、保健所等)で申請する必要があります。
臨床的重症度による分類
| 重症 | 中等度 | 軽度 | |
|
排便回数 |
6回以上 |
重症と軽症の中間 |
4回以下 |
|
顕血便 |
(+++) |
(+)~(-) |
|
|
発熱 |
37.5℃以上 |
37.5℃以上の発熱がない |
|
|
頻脈 |
90/分以上 |
90/分以上の頻脈なし |
|
|
貧血 |
Hb10g/dL以下 |
Hb10g/dL以下の貧血なし |
|
|
赤沈 |
30mm/h以上 |
正常 |
重症度
軽 症:上記の6項目を全て満たすもの
中等症:上記の軽症、重症の中間にあたるもの
重 症:1及び2の他に、全身症状である3又は4のいずれかを満たし、かつ6項目のうち4項目を満たすもの