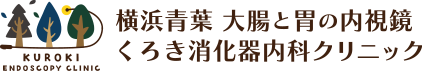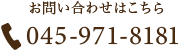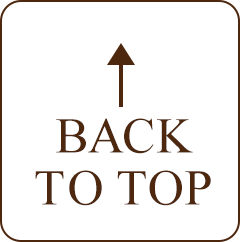便で分かる体調の変化
便をじっくり見ることは、通常ではあまりないかもしれません。
しかし便には自分の体の状態を知るためのさまざまな手がかりが含まれていると言えます。
便の形状や色、においなどから現在の体調を把握し、変化がないかを確認することで、何らかの病気の兆候にいち早く気づくことができるかもしれません。
排便回数
 健康な人は通常、1日に1~2回排便しますが、個人差があります。1日3回や1週間に3回程度であれば問題ありません。しかし、1日に5回以上排便する場合や、1週間に1~2回しか排便しない場合は、極端な下痢や便秘の可能性があります。その際は専門医に相談することをおすすめします。
健康な人は通常、1日に1~2回排便しますが、個人差があります。1日3回や1週間に3回程度であれば問題ありません。しかし、1日に5回以上排便する場合や、1週間に1~2回しか排便しない場合は、極端な下痢や便秘の可能性があります。その際は専門医に相談することをおすすめします。
便の量
便の量は、食べる量や食事の内容によって変わります。植物性食品を多く食べると便の量が多くなり、柔らかくなる傾向があります。一方、肉類を多く食べると便の量が少なくなり、硬くなる傾向があります。
1日あたりの便の平均量はおよそ100~200gで、その約80%が水分です。残りの20%は、腸内細菌、未消化の食べ物、胃や腸の分泌物、剥がれた細胞などで構成されています。また、便に含まれる脂肪は通常2g程度とされています。
便の性状
便の形状や状態から腸の感染症や炎症の有無、腸の蠕動運動の状態を推測できます。
健康な便
黄褐色でバナナ状または半固形、においはほとんどなく、柔らかくてスムーズに排便できます。
泥状または水状
これは下痢の症状です。
水状の便に粘液、血液、膿が混ざっている場合は、細菌性赤痢や感染性下痢などの感染性腸炎、または炎症性腸疾患の可能性があります。
ウサギの糞のような便
ウサギの糞のような小さく硬い便が出る場合は、大腸がけいれんしている痙攣性便秘の可能性があります。
硬くて太い便
排便時に便が硬くて太い場合は、大腸が正常に動いていない弛緩性便秘の可能性があります。
硬く、断片的な便
これは排便の衝動を我慢し続けることで直腸の感受性が低下するために起こります。
便のにおい
便のにおいは、スカトールやインドールといった物質が原因です。これらは腸内細菌がタンパク質を分解する際に作られます。便秘で便が腸内に長くとどまる場合や、肉類などの動物性タンパク質を多く摂取した場合、または消化器系の病気がある場合には、便のにおいが強くなります。特に、すい臓の病気や直腸がんがある場合は、においがより強くなることがあります。
一方で、規則正しい生活、適度な運動、食物繊維や水分の十分な摂取、脂肪の適度な摂取は腸を刺激し、排便を促す効果があります。便秘を解消することで、便やおならのにおいを軽減することができます。
緑色の便が出た?
便の色から分かること
赤色
 赤色は血液の鮮度を示し、出血が肛門に近いほど血液は新鮮です。
赤色は血液の鮮度を示し、出血が肛門に近いほど血液は新鮮です。
痔や裂肛は鮮血ですが、S状結腸や直腸からの出血には鮮血と血の塊が混ざっています。上行結腸や横行結腸からの出血は濃紫色で、便の外側に付着した血液は直腸や肛門からの出血と考えられます。このような場合には、当クリニックへ受診をおすすめします。
黄色
 ひどい下痢の場合の色です。
ひどい下痢の場合の色です。
牛乳の過剰摂取、下剤の使用、脂肪便の場合にも見られます。
黒色
 胃などの上部消化管からの出血の場合に見られます。コールタールに似ていることからタール便とも呼ばれます。また、イカ墨の料理を食べた後や、鉄分サプリメントを摂取した後、薬用炭を使用した後にも黒色の便が見られます。
胃などの上部消化管からの出血の場合に見られます。コールタールに似ていることからタール便とも呼ばれます。また、イカ墨の料理を食べた後や、鉄分サプリメントを摂取した後、薬用炭を使用した後にも黒色の便が見られます。
緑色
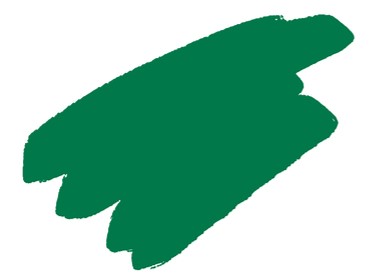 母乳を飲んでいる赤ちゃんや、葉緑素を多く含む緑黄色野菜を大量に食べた方の便は緑色になります。
母乳を飲んでいる赤ちゃんや、葉緑素を多く含む緑黄色野菜を大量に食べた方の便は緑色になります。
灰白色
 胆汁の流れが悪くなる胆道や膵臓の病気か、胃腸の透視検査中のバリウムによるものです。
胆汁の流れが悪くなる胆道や膵臓の病気か、胃腸の透視検査中のバリウムによるものです。
濃褐色
 便秘の場合や、肉類を多く食べた場合に見られる色です。
便秘の場合や、肉類を多く食べた場合に見られる色です。
また、ココアやチョコレートを大量に摂取した場合にも見られます。
茶~茶褐色
 食べ過ぎや飲み過ぎの場合に見られます。
食べ過ぎや飲み過ぎの場合に見られます。
黄褐色
 便の正常な色です。
便の正常な色です。
胆汁色素のビリルビンによるものと考えられています。
便の色に影響を及ぼす薬剤
赤色
セフジニル(抗生物質、粉ミルクや経腸栄養剤などの鉄分含有製品に色をつけるために使用)、フェノバリン
オレンジ色
リファンピシン、リマクタン(抗結核薬)
黒色
ビスマス塩製剤(下剤)、硫酸鉄(鉄剤)、プロトポルフィリンナトリウム(慢性肝疾患治療薬)、薬用炭(吸着剤)
白色
レントゲン造影用のバリウム
白色残渣
バルプロ酸ナトリウム徐放錠(抗てんかん剤;添加物の一部が溶けずに排出される)
銀白色
水酸化アルミニウム(制酸剤)などのアルミニウム塩
緑色
クロロフィル製剤(葉緑素:消化性潰瘍治療薬)
ゼリー状の便?
受診が必要な便の色
黒色便
黒色の便はコールタールのように黒く粘度があるため「タール便」とも呼ばれます。
便秘の際の濃い茶色の便を、黒色便と間違えて受診される方が多いですが、本当の黒色便は漆黒です。
このような便は、食道、胃、十二指腸から出血していることを意味します。例えば、胃潰瘍や胃がんからの出血があると、胃酸によって血液中の鉄分が酸化され、黒い便が出ます。一方、大腸からの出血であれば胃酸の影響を受けませんので、便は黒くなりません。また、貧血の治療で鉄剤を服用している場合も黒色便が出ます。
赤いゼリー状の血便
赤いゼリー状の血便が見られる場合は注意が必要です。これが続くと、「慢性腸炎」の可能性が考えられます。通常、便に血が混じることはありませんが、このようなゼリー状の出血は「大腸粘膜からのゆっくりとした出血」を示している可能性があります。
痔など血管に関係する病気の場合、出血は多く液体状であることが一般的です。一方で、腸の粘膜からの出血はゼリー状になることがあります。この症状は、特に若い人に多い潰瘍性大腸炎という原因不明の慢性腸炎でよく見られ、粘液が混ざることもあります。また、赤痢アメーバによる感染性腸炎でも同様のゼリー状の血便が見られることがあります。
このような症状がある場合は、早めに専門医に相談することをおすすめします。
細い便
次に注意すべきは、「細い便」です。通常、便の太さはバナナくらいが正常とされています。しかし、便が「突然」細くなり、その状態が「続く」場合は注意が必要です。これは、大腸がんによって大腸が狭くなっている可能性を示していることがあります。
一時的に便が細くなることは、食事内容や腸の動きの影響で誰にでも起こるものです。しかし、大腸がんで大腸が狭くなっている場合、腸管が広がらなくなるため、細い便が長期間続くことがあります。
ただし、大腸がんだからといって必ずしも便が細くなるわけではありません。このような症状がある場合は、早めに医師に相談することをおすすめします。
血が付着する便
排便時に便の表面に血が付着することがありますが、これは大腸がんに見られる一般的な症状の一つです。特に、大腸がんが発生しやすいS状結腸や直腸にがんがある場合、便自体は正常に見えても、がんがある部分を通過する際に出血し、その血が便の表面に付着して排出されることがあります。
がんによる出血は、少量のにじむようなものから大量出血までさまざまです。一方、痔の場合は静脈からの出血が多く、血の性状は「液状」であることが一般的です。そのため、便の表面に血液がねばねばとした層のように付着している場合は注意が必要です。
このような症状が続く場合は、早めに医師に相談しましょう。
灰白色便
灰白色便とは、その名の通り「白っぽい」便のことです。「そんなに白い便が出るのか」と驚くかもしれませんが、胆管がん、すい臓がん、総胆管結石などの病気によって発生することがあります。
通常の便が黄色いのは、「胆汁」と呼ばれる物質が関係しています。胆汁は肝臓で作られ、胆嚢に貯められた後、胆管を通って十二指腸に分泌される消化酵素です。この胆汁が便に混ざることで、便は黄色くなります。
しかし、胆管がんや総胆管結石などの病気で胆汁の流れが妨げられると、胆汁が十二指腸に届かなくなり、便の色が黄色ではなく白っぽくなります。また、胆汁が腸に流れず血液中に逆流すると、黄疸(目や皮膚が黄色くなる症状)を引き起こすことがあります。さらに、胆汁が尿に流れる場合には、尿が褐色(お茶のような色)になることもあります。
これらの症状が見られる場合は、早めに医師に相談しましょう。