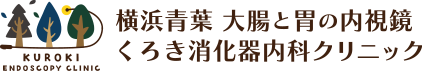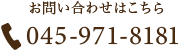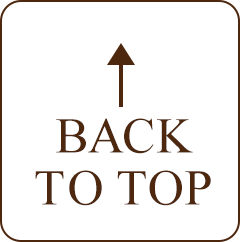内科とは
 内科は、日常生活で起こるさまざまな症状に対応する診療科です。急性的な症状(咳、喉の痛み、頭痛、腹痛、吐き気・嘔吐、下痢、便秘、めまい、動悸、息切れ、背中や腰の痛み、しびれなど)の診察・治療を行う他、慢性的な症状(高血圧、糖尿病、脂質異常症、花粉症、アレルギーなど)の継続的な治療にも対応しています。また、かかりつけ医として幅広い病気に対する初期診療を行います。より専門的な検査や治療が必要な方には、当クリニックが提携している医療機関をご紹介し、最適な治療をお受けいただけるよう全面的にサポートします。どこに相談したら良いかわからない、体に不調がある、など気になることがあれば、まずは当クリニックにご相談ください。
内科は、日常生活で起こるさまざまな症状に対応する診療科です。急性的な症状(咳、喉の痛み、頭痛、腹痛、吐き気・嘔吐、下痢、便秘、めまい、動悸、息切れ、背中や腰の痛み、しびれなど)の診察・治療を行う他、慢性的な症状(高血圧、糖尿病、脂質異常症、花粉症、アレルギーなど)の継続的な治療にも対応しています。また、かかりつけ医として幅広い病気に対する初期診療を行います。より専門的な検査や治療が必要な方には、当クリニックが提携している医療機関をご紹介し、最適な治療をお受けいただけるよう全面的にサポートします。どこに相談したら良いかわからない、体に不調がある、など気になることがあれば、まずは当クリニックにご相談ください。
発熱時の対応について
当院では発熱患者様の診察は承っておりませんので、予めご了承ください。
内科でよくある症状
症状としてはよくあるものですが、重大な病気が隠れている場合もありますので注意が必要です。早期発見・早期治療の観点から、少しでも気になる症状や違和感などあれば、お気軽に当クリニックへご相談ください。
内科でよくある病気
糖尿病
 糖尿病は、すい臓から分泌されるホルモンであるインスリンの働きが低下し、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が上昇して起こる病気です。糖尿病には、1型糖尿病、2型糖尿病、その他の特定の機序・疾患による糖尿病があります。
糖尿病は、すい臓から分泌されるホルモンであるインスリンの働きが低下し、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が上昇して起こる病気です。糖尿病には、1型糖尿病、2型糖尿病、その他の特定の機序・疾患による糖尿病があります。
日本では、生活習慣病のひとつである2型糖尿病が中高年層に多くみられます。
インスリンの分泌低下に加えて、過食、運動不足、肥満、ストレスなども糖尿病の発症に関係しているとされています。糖尿病が進行すると、神経障害、網膜症、腎症などの合併症につながる可能性があるので、定期的な健康診断と早期発見、生活習慣の改善が重要です。
高血圧
 高血圧が続くと血管の壁への負担が大きく、動脈硬化につながるリスクが高まります。原因は塩分過多など偏った食生活、飲酒、喫煙、運動不足、ストレスなどの要因が相互に影響し合って引き起こされると言われています。
高血圧が続くと血管の壁への負担が大きく、動脈硬化につながるリスクが高まります。原因は塩分過多など偏った食生活、飲酒、喫煙、運動不足、ストレスなどの要因が相互に影響し合って引き起こされると言われています。
高血圧を放置すると心臓病や脳卒中、腎障害などの発症リスクが高まるため、血圧を正常値に近づけるよう治療が必要です。予防と管理には塩分を控えたバランスの良い食事や適度な運動、ストレス管理が重要です。
脂質異常症
血液中のコレステロールや中性脂肪といった脂質のバランスが崩れた状態です。高カロリーの食事、飲酒、喫煙、運動不足などの生活習慣の影響や遺伝的要因が原因で発症します。
放置すると動脈硬化につながり、脳卒中や心筋梗塞などを引き起こす可能性があるので注意が必要です。コレステロールは、悪玉コレステロール(LDL)と善玉コレステロール(HDL)の2つに分けられます。善玉コレステロールは血管や細胞にたまった余分な脂質を肝臓に戻す働きがあるので、余分なコレステロールを減らす働きがあります。
高尿酸血症
 血液中の尿酸値が上昇した状態が高尿酸血症です。尿酸の結晶が関節に蓄積して炎症を引き起こす痛風の原因となります。
血液中の尿酸値が上昇した状態が高尿酸血症です。尿酸の結晶が関節に蓄積して炎症を引き起こす痛風の原因となります。
症状は足の親指などに突然激しい痛みや腫れが生じる痛風発作があります。
尿酸値が高いまま放置すると、痛風だけでなく尿酸結石や、それが蓄積して腎障害を引き起こす可能性があるので注意してください。
治療には、尿酸生成抑制薬や尿酸排泄促進薬などの内服薬を用いますが、プリン体を摂り過ぎないように日頃の食生活を見直すことも重要です。
貧血
 血液中の赤血球やヘモグロビンの量が正常値を下回り、全身に酸素が十分に供給されない状態が貧血です。
血液中の赤血球やヘモグロビンの量が正常値を下回り、全身に酸素が十分に供給されない状態が貧血です。
症状として疲れやすさや息切れ、めまいなどが挙げられます。原因は出血やビタミン不足などがあり、中でも鉄分不足による鉄欠乏性貧血が最も多く、女性や高齢者に多くみられます。また、胃がんや大腸がん、潰瘍性大腸炎といった病気の症状として貧血が起こることもあります。貧血と言われたたり、お悩みの方は、お気軽に当クリニックへご相談ください。
インフルエンザ
 インフルエンザはインフルエンザウイルスが原因の感染症で、通常は寒い季節に流行します。発熱、頭痛、全身の倦怠感、筋肉痛、関節痛、咳、鼻水、喉の痛みなどの症状があります。1週間以内に回復することが大半ですが、中には肺炎や脳症などの合併症が引き起こすこともありますので、注意が必要です。季節性インフルエンザは強い感染力があり、特に高齢者や基礎疾患を持つの方、小児は注意が必要です。当クリニックではインフルエンザワクチンの予防接種も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
インフルエンザはインフルエンザウイルスが原因の感染症で、通常は寒い季節に流行します。発熱、頭痛、全身の倦怠感、筋肉痛、関節痛、咳、鼻水、喉の痛みなどの症状があります。1週間以内に回復することが大半ですが、中には肺炎や脳症などの合併症が引き起こすこともありますので、注意が必要です。季節性インフルエンザは強い感染力があり、特に高齢者や基礎疾患を持つの方、小児は注意が必要です。当クリニックではインフルエンザワクチンの予防接種も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
花粉症
 花粉症はスギなど植物の花粉が原因で起こるアレルギー性疾患で、日本国内では約60種類の植物がアレルギー源として知られています。主な症状は、くしゃみや鼻水など鼻の症状、目の痒みや充血など目の症状ですが、人によっては咳や頭痛、発熱、皮膚の痒み、喉の痒みや痛みなど、さまざまな症状が生じることがあります。
花粉症はスギなど植物の花粉が原因で起こるアレルギー性疾患で、日本国内では約60種類の植物がアレルギー源として知られています。主な症状は、くしゃみや鼻水など鼻の症状、目の痒みや充血など目の症状ですが、人によっては咳や頭痛、発熱、皮膚の痒み、喉の痒みや痛みなど、さまざまな症状が生じることがあります。
骨粗鬆症
骨粗鬆症は骨密度(骨量)が減少し、骨がもろく骨折しやすくなった状態です。骨粗鬆症が進行すると、ご自身の体重によって圧縮された背骨などが折れることもあります。
女性ホルモンの減少や老化が関係しているといわれ、閉経後の女性や高齢の方は骨密度が低下しやすいため、定期的に骨密度検査を受けることが推奨されています。
高齢の方の場合、骨折すると寝たきりの原因になりやすいので、骨密度の低下を未然に防ぐことが大切です。薬による治療も行いますが、日頃からカルシウムなどの栄養素を十分に摂り、ウォーキングなどの軽い運動を習慣的に行い、骨を刺激することが骨密度の低下を防ぐのに効果的です。