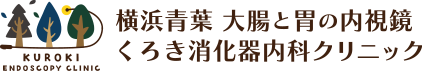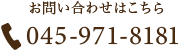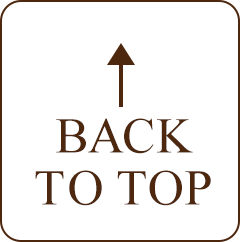胸焼けでお困りの方へ
 胃の辺りから喉にかけて、焼けるような、チリチリと刺すような感覚が起こる状態を胸焼けと言います。胸焼けの症状は人によってさまざまです。胸が熱い、胸がつかえる、背中が張る、食後に酸っぱいものがこみ上げる(呑酸)など、多岐にわたります。
胃の辺りから喉にかけて、焼けるような、チリチリと刺すような感覚が起こる状態を胸焼けと言います。胸焼けの症状は人によってさまざまです。胸が熱い、胸がつかえる、背中が張る、食後に酸っぱいものがこみ上げる(呑酸)など、多岐にわたります。
健康な方でも、脂っこいものを食べ過ぎたり、お酒やコーヒーを飲み過ぎたりすると、この感覚が一時的に現れることがあります。しかし、この感覚が長く続く場合は、胃や食道に重大な病気が隠れている可能性があります。
胃酸の分泌を抑える薬を服用することで胸焼けの症状は消失しますので、治ったように感じられます。しかし、食道や胃などに病気がある場合や胃の機能が衰えている場合は、症状が繰り返すことがあります。まずはお気軽に当クリニックへご相談ください。
胸焼けの原因
食生活の乱れ
食べ過ぎや飲み過ぎは胃に大きな負担をかけます。胃が早く飲食物を消化しようとして胃酸の分泌が過剰になったり、消化中の飲食物に含まれる刺激物に胃が過剰に反応したりすることで、胃酸を含んだ消化物が食道に逆流し、胸焼けや酸っぱいゲップ(胃酸の逆流)、喉のつまり感などの症状を引き起こします。
胃を刺激する代表的な飲食物には、脂肪分を多く含む食品、お酒、また過剰な香辛料、カフェインなどがあります。
加齢、肥満による食道括約筋機能の低下
下部食道括約筋は、食道と胃の境目にある筋肉で、食べ物が通るときに胃の入り口を閉じて胃の中身が食道に逆流しないようにしています。この筋肉が何らかの原因で緩むと、機能が低下して胃から食道へ逆流が起こります。
下部食道括約筋が緩む主な原因として、加齢や肥満による腹圧の上昇などが考えられます。また、食道と胃は横隔膜の隙間(食道裂孔)でつながっていますが、胃がこの裂孔から胸の方へ飛び出している状態を食道裂孔ヘルニアといい、高齢の方に多く見られます。食道裂孔ヘルニアがある方は、胃液や胃の内容物が逆流しやすくなり、胸焼けの原因となります。
姿勢
 通常、胃と食道は縦の関係にあり、食べ物が逆流しにくい構造になっています。しかし、猫背や前かがみの姿勢になると、胃が圧迫され押し上げられ、胃酸が逆流しやすくなります。
通常、胃と食道は縦の関係にあり、食べ物が逆流しにくい構造になっています。しかし、猫背や前かがみの姿勢になると、胃が圧迫され押し上げられ、胃酸が逆流しやすくなります。
特に、仰向けになることは典型的な例です。寝る前に何か食べると胃酸が出やすい状態になり、就寝中に口に酸っぱいものがこみ上げることがあります。
ストレス
消化管は基本的に自律神経によって支配されています。そのため、ストレスなどの心理的刺激により自律神経のバランスが乱れると、食道や胃の運動、下部食道括約筋の機能、蠕動運動に異常をきたしたり、胃酸の過剰分泌が起こったりします。
ピロリ菌
ピロリ菌に感染して胃の中に棲みつくと、慢性的な炎症を引き起こし、潰瘍やびらんになりやすいことが知られています。
慢性胃炎になると、胃もたれや吐き気、胸焼けなどの症状が現れることがあります。この状態が続くと、胃の粘膜が委縮する萎縮性胃炎となり、胃がんのリスクが高まります。これらの状態は、ピロリ菌の除菌で改善が期待できます。除菌後は萎縮性胃炎が改善され、一時的に胸焼けなどの症状が悪化することがありますが、多くの場合は一過性です。検査でピロリ菌感染が判明した場合は、除菌をお勧めします。
胸焼けの症状を起こす病気
逆流性食道炎(胃食道逆流症)
下部食道括約筋や食道蠕動運動、胃の噴門付近の異常により、胃酸が食道内に逆流し、いろいろな症状を引き起こす病気を胃食道逆流症(Gastro Esophageal Reflex Disease:GERD)といいます。消化中の食べ物や胃酸そのものが食道に逆流する病気です。逆流性食道炎は、これによって炎症が起こる病気です。
胃酸には強力な酸のほか、タンパク質を分解する酵素が含まれています。胃壁はこれらの刺激物に耐えられる構造になっていますが、食道にはその構造がありません。そのため、逆流が起こると炎症が引き起こされ、びらんや潰瘍へと発展します。そして胸焼けや慢性的な咳、喉の違和感などの症状を引き起こし、食道がんのリスクも高まります。
特に近年は、食生活の欧米化に伴い、若年層でもこの病気の発生率が高まっています。気になる症状のある方は、ぜひ一度当クリニックへご相談ください。
慢性胃炎
慢性胃炎は、長期間にわたる炎症の繰り返しにより、胃の粘膜が委縮した病気です。 胃痛・胃もたれ、膨満感、吐き気、時には胸焼けなどの不調を感じることがあります。
原因はピロリ菌によるものが多いと考えられています。ピロリ菌に感染すると炎症を起こすだけでなく、潰瘍やポリープ、胃がんの原因にもなります。
慢性的に胃の調子が悪い方は、ピロリ菌の検査を受け、陽性反応が出た場合は除菌することをお勧めします。
胃・十二指腸潰瘍
胃には通常、胃酸が自らの組織を侵食するのを防ぐ保護機能があります。しかし、何らかの理由でこの機能がバランスを崩すと、胃酸が胃と十二指腸の粘膜を溶かし、組織に炎症を引き起こします。この炎症が進行し、粘膜の下にある粘膜下層にまで損傷が広がると、潰瘍が形成されます。
胃潰瘍と十二指腸潰瘍は、どちらも痛みを引き起こすほか、腹部膨満感、吐き気、胸焼けなどの症状が現れることがあります。胃潰瘍の場合は吐血や嘔吐物に血が混ざることもあり、十二指腸潰瘍の場合は加えて下血(黒っぽい便)が見られることもあります。
胃潰瘍は食後に、十二指腸潰瘍は空腹時に痛みが強くなると言われています。
胸焼けに対する検査
 問診では、症状の詳細、持病の有無、服薬中の薬についてお聞きし、食道や胃に異常が疑われる場合は胃カメラ検査を行います。胃カメラ検査では、食道の粘膜を詳しく調べることができ、逆流性食道炎、ポリープ、好酸球性食道炎、食道カンジダ症などのほか、食道がんの有無を調べることができます。また、検査中に組織を採取し、病理検査を行うことで、確定診断を行うことも可能です。当クリニックでは苦痛の少ない胃カメラ検査を実施しており、経験豊富な専門医が担当しています。気になる症状のある方は、当クリニックへご相談ください。
問診では、症状の詳細、持病の有無、服薬中の薬についてお聞きし、食道や胃に異常が疑われる場合は胃カメラ検査を行います。胃カメラ検査では、食道の粘膜を詳しく調べることができ、逆流性食道炎、ポリープ、好酸球性食道炎、食道カンジダ症などのほか、食道がんの有無を調べることができます。また、検査中に組織を採取し、病理検査を行うことで、確定診断を行うことも可能です。当クリニックでは苦痛の少ない胃カメラ検査を実施しており、経験豊富な専門医が担当しています。気になる症状のある方は、当クリニックへご相談ください。
ひどい胸焼けを今すぐ治したい方の対処法
お腹を強く締めつけない
お腹を締め付け過ぎると、腹腔内の圧力が高まり、胃酸が逆流しやすくなります。
胸焼けが起こりやすい方は、お腹を締め付けないデザインのゆったりとした服装がお勧めです。猫背の方は姿勢を正すように心掛け、また、肥満体型の方は、徐々に体重や腹囲の減量を目指すことも大切です。
就寝時の姿勢を工夫する
頭を高くして寝ると、胸焼けを予防できるとされているので、試してみてください。また、体の左側を下にする姿勢では胃より食道の位置が高いため、逆流した酸が早く排除されるといわれています。その結果、胸焼けを予防でき、睡眠の質を改善することができます。
チョコレート、コーヒー、炭酸飲料などを避ける
油ものやチョコレートなどの高脂肪食、香辛料を多く含んだ食事、コーヒーなどのカフェインを多く含む飲料、アルコール、炭酸飲料、ミカンなどの柑橘類などの刺激物は胃酸過多引き起こしやすいとされています。また、喫煙は食道運動機能を低下させ、胃酸逆流を悪化させます。
胸焼けを起こしやすい方はこれらの食品や飲料を避けることをお勧めします。喫煙者の方は禁煙を目指しましょう。
市販薬を活用する
H2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)や選択的ムスカリン受容体拮抗薬(M1ブロッカー)などの胃酸を抑える市販薬も、胸焼けの症状緩和に役立つことがあります。
胃酸を抑える薬で効果が十分でない場合は、胃の運動を改善する薬や漢方薬なども選択肢となります。生活習慣の改善や市販薬でも症状が改善しない場合は、医療機関において、胃酸分泌抑制薬(主にプロトンポンプ阻害薬やカリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB))による治療を行います。胸焼けでお悩みの方は、お気軽に当クリニックへご相談ください。