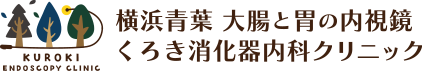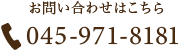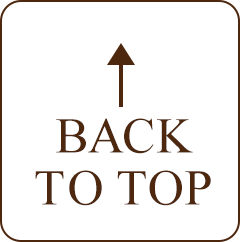専門医が診る消化器内科・内視鏡内科
 当クリニックの消化器内科・内視鏡内科では、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸に加え、胆のう、すい臓、肝臓など、消化に関わる臓器全般に関するお悩みに対応しています。
当クリニックの消化器内科・内視鏡内科では、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸に加え、胆のう、すい臓、肝臓など、消化に関わる臓器全般に関するお悩みに対応しています。
「なんとなく胃が重い」「お腹の調子が悪い」といった日常の不調から、嚥下しづらさ、吐き気・嘔吐、腹痛、下痢・便秘、血便などの症状まで、幅広く診察いたします。また、発熱や貧血など、消化器の病気が隠れていて、診断が難しい場合がありますので、消化器内科や内視鏡内科で正確な診断を受けることが大切です。
当クリニックでは、経験豊富な専門医が最適な検査と治療をご提案し、安心して治療をうけていただけるよう心掛けています。消化器の不調が気になる際は、お気軽にご相談ください。
消化器内科・内視鏡内科で
よくある症状
その他症状
- 肝障害など
- 健康診断やがん検診での異常所見
- バリウム検査での異常所見
- 便潜血検査陽性
- 全身の倦怠感
- 体重の減少など
消化器内科・内視鏡内科で
よくある病気
食道の病気
胃食道逆流症(GERD)・逆流性食道炎
胃酸が食道内に逆流し、いろいろな症状を引き起こす病気を胃食道逆流症(Gastro Esophageal Reflex Disease:GERD)といい、胃酸により食道の粘膜に炎症が起こる病気が逆流性食道炎です。不規則な生活習慣、喫煙、飲酒、肥満、加齢、食道裂孔ヘルニアなどが原因として考えられます。
一般的な症状としては、胸焼け、胸痛、喉の違和感、吐き気、口の中の苦味、慢性的な咳などがあります。また、慢性の胃食道逆流症(GERD)・逆流性食道炎により、食道の粘膜が胃の粘膜に置き換わる状態(バレット食道)と診断された方も要注意です。
問診や内視鏡検査を通じて正確な診断を行い、薬物療法や生活習慣の改善指導が必要となってきますので、胸焼けなどの不快な症状にお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
食道がん
 食道がんは、食道に発生する悪性腫瘍で、主に飲酒や喫煙が発症リスク要因とされています。初期の食道がんの多くは、目立った自覚症状がほとんど現れません。しかし進行すると、胸の違和感や飲み込みにくさなどの症状が現れてきます。
食道がんは、食道に発生する悪性腫瘍で、主に飲酒や喫煙が発症リスク要因とされています。初期の食道がんの多くは、目立った自覚症状がほとんど現れません。しかし進行すると、胸の違和感や飲み込みにくさなどの症状が現れてきます。
早期発見と治療が重要で、内視鏡検査が診断に有効です。症状やリスクに応じて内視鏡検査を実施することが大事です。
胃・十二指腸の病気
胃炎
急性胃炎
症状としては、激しい腹痛、胃の不快感、吐き気、ひどい場合には黒色便や吐血も見られます。過度の飲酒や刺激の強い食事、ストレス、ピロリ菌への感染、アレルギー、鎮痛剤や抗菌剤の使用などが急性胃炎を引き起こす原因として挙げられます。
一部の症例では、炎症が胃粘膜の広範囲にわたり、これを急性胃粘膜病変と言います。
慢性胃炎
主にピロリ菌の感染によって発症します。代表的な症状には、胃もたれやみぞおちの痛み、腹部の不快感、腹部膨満感、食欲不振などがありますが、無症状の場合も少なくありません。放置すると胃潰瘍や胃がんのリスクが高まることがあります。健康診断などでピロリ菌感染が陽性となった場合は、内視鏡検査(胃カメラ検査)で胃の状態をチェックし、その上で除菌治療が推奨されます。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃や十二指腸の粘膜が傷つき、炎症が生じる病気です。主な原因はピロリ菌感染で、他には過度な飲酒、ストレス、鎮痛薬の長期投与などが挙げられます。
症状として、みぞおちや背中の痛み、胃もたれ、腹部の張り、吐き気などがあります。場合によっては潰瘍から出血し、吐血や黒色便が現れることがあります。
内視鏡検査を用いた診断と、ピロリ菌除菌や薬物療法などが必要となります。
胃ポリープ
バリウム検査で発見されることが多く、ポリープ自体に自覚症状はほぼ現れません。
胃カメラ検査で具体的なポリープの種類について調べる必要があります。
胃底腺ポリープ
胃の粘膜にできる良性のポリープで、主に胃の上部(胃底部)に発生します。多くの場合、症状はなく健康診断(バリウム)や内視鏡検査(胃カメラ)で偶然発見されます。まれにがん発生の報告もありますが、一般的にはがん化のリスクが低く、経過観察で問題ありません。ピロリ菌に感染していない健康な胃に出来ることが多いとされています。
過形成性ポリープ
胃の粘膜が過剰に増殖してできるポリープで、ピロリ菌感染が原因になることが多いです。多くの場合、治療の必要はありませんが、まれにがん化するリスクや、貧血の原因となる場合があるので、定期的に内視鏡検査(胃カメラ)を受け、ポリープを注意深く観察することをおすすめします。
胃腺腫
胃腺腫は、胃の粘膜にできる良性と悪性の中間的なポリープですが、一部が胃がんに進行する可能性があるため注意が必要です。多くの場合、症状はなく内視鏡検査(胃カメラ)で発見されますが、早期発見と適切な治療(内視鏡による切除など)が重要です。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアとは、胃カメラ検査などでは異常が見つからないものの、胃痛や胃もたれなどの症状が続く病気です。機能性胃腸症とも呼ばれます。
そもそも、逆流性食道炎や胃炎が胃カメラ検査で発見された場合でも、症状が無い場合も多く、逆に症状があっても検査で異常が見つからないこともあります。そのため、胃カメラ検査で所見があってもなくても、症状を説明できる異常が見つからない状態を「機能性ディスペプシア」と診断されることがあります。
胃がん
胃がんは胃の内側の粘膜から発生するがんで、初期段階では症状がないことが多いため注意が必要です。
進行すると周囲に広がり、他の臓器やリンパ節にも転移することがあります。原因としては喫煙、食生活の乱れ、ピロリ菌感染が挙げられます。早期に発見できれば内視鏡治療で完治が望めますので、定期的な胃カメラ検査をおすすめします。
スキルス胃がん
スキルス胃がんは、胃がん全体の約10%を占める病態で、胃壁の内部を這うように広がるため、発見が困難とされています。診断時には多くの場合すでに進行しており、60%以上に転移が見られます。このタイプの胃がんは増殖が速く、胃カメラ検査でも早期発見が難しいのが特徴です。技術の進歩により一般的な胃がんは早期発見が可能になっていますが、スキルス胃がんには進行した段階で診断されることがほとんどです。
さらに、腫瘍が胃壁の外側に進展すると、腹腔内に広がり腹膜播種を引き起こす場合があります。腹膜播種は手術による完全除去が難しく、主に抗がん剤などの化学療法を用いた治療になります。将来的には、免疫療法や遺伝子治療の発展による新たな治療法の確立が期待されています。
ピロリ菌
ピロリ菌は幼少期に口を通じて体内に入り、胃に定着する細菌です。感染すると、成人後に萎縮性胃炎を引き起こし、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、さらには胃がんのリスクを高める可能性があります。
また、胃MALTリンパ腫や免疫性血小板減少性紫斑病の原因となることもあります。ピロリ菌は内服薬で除菌が可能ですので、気になる方はお気軽に当クリニックまでご相談ください。
アニサキス症
アニサキスはサバやイカなどの魚介類に寄生する虫で、生のまま食べることで感染することがあります。
感染すると激しい腹痛や吐き気、嘔吐といった症状を引き起こしますが、胃カメラ検査でアニサキスを取り除けば、症状は速やかに改善します。当クリニックでは胃カメラ検査を行っていますので、思い当たる節があり、急な激しい腹痛でお困りの際は、ぜひご相談ください。
大腸の病気
大腸ポリープ
 大腸ポリープは、大腸の粘膜が増殖して隆起してくるものです。その形や大きさはさまざまで、1mmほどの小さなものから数cmに達するものまであります。
大腸ポリープは、大腸の粘膜が増殖して隆起してくるものです。その形や大きさはさまざまで、1mmほどの小さなものから数cmに達するものまであります。
ポリープには、非腫瘍性と腫瘍性の2種類があり、腫瘍性ポリープは切除の対象となります。腫瘍性ポリープには、大腸ポリープの80%以上を占めるといわれる腺腫や、いわゆるがんが含まれます。遺伝的な要因や、食生活の欧米化が原因と考えられています。当クリニックでは、大腸カメラ検査中に発見された大腸ポリープをその場で切除する「日帰り大腸ポリープ切除」を行っています。
大腸がん
大腸がんは初期には自覚症状がほとんどないため、病気が進行した状態で発見されることもよくあります。
近年では食生活の欧米化により、大腸がん患者数は増加傾向にあると言われています。
大腸がんは大腸カメラで発見できるため、下痢や便秘、血便などの症状に心当たりのある方は、早めに大腸カメラ検査の受診をおすすめします。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome:IBS)は腹痛や不快感とともに、便通の異常(下痢や便秘)を繰り返す機能性消化管障害です。
主な症状として、繰り返す腹痛や腹部不快感や便通の異常(下痢または便秘、あるいはその繰り返し)、お腹の張り感、排便後の残便感などがあります。大腸カメラや腹部CTスキャンの検査で異常が見つからず、症状の程度は人によって大きく異なります。また、ストレスや食事により症状が変化することが特徴です。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、大腸粘膜に炎症が起こる原因不明の慢性の炎症性腸疾患です。
本邦では年々増加傾向にあり、20~30歳代に多い傾向がありますが、若年者から高齢者まで発症します。多くは直腸から連続性に口側(奥側)に広がっていき、炎症の範囲によって、直腸型、左側結腸炎型、全結腸炎型に分類されます。
腹痛、下痢、粘血便などの症状が見られ、長期にわたって大腸の粘膜が炎症を繰り返すと、そこに大腸がんが発生することもあります。
当クリニックでは、潰瘍性大腸炎をはじめとする炎症性腸疾患の診断や治療を専門的に行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
クローン病
クローン病は、口腔から肛門にいたるまでの消化管のどの部位にも炎症(粘膜のただれ)や潰瘍(粘膜の欠損)が起こり得る、原因不明の慢性の腸管炎症です。主として若年者にみられ、小腸と大腸を中心として腸管炎症が起こり、腹痛や下痢、血便、体重減少、肛門の病変(痔ろうなど)が生じます。
薬物療法の進歩により、以前よりも予後が向上しています。しかし、症状が表に現れにくいケースも多く、ひそかに病気が進行し、腸の狭窄や穿孔に繋がる場合もあります。
当クリニックではクローン病をはじめとする炎症性腸疾患の診断や治療を専門的に行っています。この病気は疑わないと診断が難しいこともありますので、少しでも気になる症状がある際は、お気軽にご相談ください。