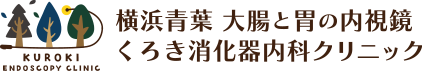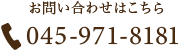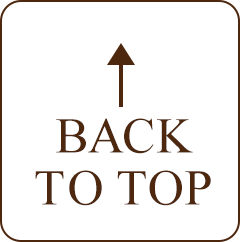便潜血陽性の方へ
 便潜血検査は、便に血液が混じっているかを調べる簡単な検査です。便を専用の棒でこするだけで、目では見えないごく少量の血液も見つけることができます。この検査は大腸がんを早期発見するための大切な健康診断項目の一つです。
便潜血検査は、便に血液が混じっているかを調べる簡単な検査です。便を専用の棒でこするだけで、目では見えないごく少量の血液も見つけることができます。この検査は大腸がんを早期発見するための大切な健康診断項目の一つです。
見た目で便に血が付いていたり、肛門から出血があれば病院に行く人は多いものです。しかし、便潜血検査は、そうした目に見える症状が出る前の段階で異常を見つけることができます。
残念ながら、便潜血検査で陽性と判定されても、「特に症状がないから大丈夫だろう」と考えて放置してしまう人が多いのが現状です。しかし、これは危険な考え方です。陽性と出たら、がんなどの病気の可能性もあるため、必ず消化器内科で精密検査を受けることが大切です。
早めの受診で、もしも病気があった場合でも早期発見・早期治療につながります。ご自身の健康のために、検査結果を軽視せず、きちんと対応しましょう。
便潜血検査で陰性と出たら、大丈夫なの?
便潜血検査で陰性という結果が出ても、必ずしも大腸がんでないとは限りません。この検査は大腸がんのスクリーニング検査の一つですが、必ずしもすべての大腸がんを見つけられるわけではありません。陰性結果は、検査を受けた2日間の便に血液が含まれていなかったということだけを示しています。
以下のような症状がある場合は、便潜血検査が陰性でも、大腸カメラ検査をお勧めいたします。
- 慢性的な便秘
- 継続する下痢
- いつもより細い便が続く
- 腹痛が続く
このような症状でお悩みの方は、お気軽に当クリニックまでご相談ください。より詳しい検査の必要性について、丁寧にご説明させていただきます。
便潜血、血便、下血とは
 出血と聞くと真っ赤な血を想像しがちですが、色調はさまざまで、鮮血(血液の量が多く鮮やかな赤色)、赤褐色(暗い赤色)、黒褐色(イカ墨や海苔のような色)などがあります。便に混ざった血液は、肉眼で確認できるものもあれば、便を検査しなければわからないものもあります。
出血と聞くと真っ赤な血を想像しがちですが、色調はさまざまで、鮮血(血液の量が多く鮮やかな赤色)、赤褐色(暗い赤色)、黒褐色(イカ墨や海苔のような色)などがあります。便に混ざった血液は、肉眼で確認できるものもあれば、便を検査しなければわからないものもあります。
「下血」とは、胃や十二指腸などの上部消化管からの出血を指し、黒色の便が肛門から排出されます。「血便」とは、鮮血または血液が混ざった便が肛門から排出されることを意味し、主に大腸や肛門からの出血を指します。「便潜血」とは、腸管からの出血のうち肉眼では見えない程度の出血を指し、大腸がん検診などに用いられます。この検査では、少量の出血でも異常を発見することが可能です。
便に混ざる血液について
出血と聞くと真っ赤な血をイメージしがちですが、実際にはさまざまな色があります。
- 鮮血:鮮やかな赤色で、血液の量が多い場合に見られます。
- 赤~黒褐色:暗い赤色で、腸内である程度変化した血液です。
「下血」「血便」「便潜血」の違い
- 下血:胃や十二指腸などの上部消化管からの出血により、黒色便(イカ墨のようなタール便)が肛門から排出される状態です。
- 血便:鮮血や血液が混ざった便が肛門から排出されることで、主に大腸や肛門からの出血に関連します。
- 便潜血:腸管からのわずかな出血で、肉眼では確認できないものです。便潜血検査は、大腸がん検診で異常の早期発見に役立ちます。
近年、大腸がんの患者数が増加しています。初期段階では、便の色や形に変化がなく、自覚症状もほとんどありません。そのため、便潜血検査を活用して少量の出血でも早期に発見することが重要です。気になる症状や不安がある方は、ぜひ一度検査をご検討ください。
便潜血検査は、どれくらいの精度?
便潜血検査で陽性と診断された場合、精密検査で大腸がんが見つかる確率は2~3%程度といわれています。このため、全体的な精度はそれほど高くありません。
しかし、便潜血検査の感度(大腸がんがある場合に陽性と判定される確率)は、がんの進行度や算出方法によって異なりますが、30.0~92.9%とされています。
また、大腸がんがなくても便潜血反応が陽性となる場合があり、その一例として大腸ポリープが挙げられます。特に、これまで一度も精密検査を受けたことがない方が便潜血検査で陽性になった場合は、大腸カメラ検査を受けることをおすすめします。
適切なタイミングでの精密検査は、早期発見や予防に繋がります。不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
便潜血検査の精密検査は
大腸カメラ
 消化器内科を受診すると、おそらく医師から大腸カメラ検査をすすめられるでしょう。
消化器内科を受診すると、おそらく医師から大腸カメラ検査をすすめられるでしょう。
その際、患者さんの中には便潜血検査を再度希望される方がいらっしゃいます。しかし、再検査が陰性だった場合でも、それは検査を受けた2日間の便に血液が含まれていなかったということを示してるだけで、必ずしも大腸がんを否定するものではありません。大腸がんに限らず、ポリープや他の病気が見つかる場合もあります。そのため、便潜血検査で陽性と診断された際には、大腸カメラ検査を受けることをおすすめします。
大腸カメラの長所と短所
長所
- 小さな病変も発見可能
5mm以下の小さなポリープや病変を見つけることができます。 - その場で治療が可能
病変を発見した場合、その場で切除や組織採取が可能です。 - 粘膜の詳細な観察が可能
粘膜の色や微細な模様まで観察でき、正確な診断につながります。
短所
- 準備が大変
検査前に腸をきれいにする処置が必要で、手間がかかります。 - 検査時の不快感
カメラを挿入する際に、腹部に違和感や痛みを感じることがあります。 - 腸壁への影響
カメラが腸壁に触れて傷つける可能性があります。ただし、これが原因で重大な問題が起こることは非常に稀です。
大腸カメラ検査には長所と短所がありますが、早期発見や診断の正確性を考えると、非常に有効な検査です。不安な点があれば、ぜひ医師にご相談ください。
当クリニックの
大腸カメラ検査の特徴
 当クリニックでは、患者さんの負担をできるだけ軽減するため、鎮静剤を使用した大腸カメラ検査を行っています。鎮静剤を使用することで、リラックスした状態で検査を受けていただけます。リラックスすると消化管の動きが緩やかになり、大腸カメラが挿入しやすくなるため、粘膜全体をくまなく観察でき、より質の高い検査が可能です。
当クリニックでは、患者さんの負担をできるだけ軽減するため、鎮静剤を使用した大腸カメラ検査を行っています。鎮静剤を使用することで、リラックスした状態で検査を受けていただけます。リラックスすると消化管の動きが緩やかになり、大腸カメラが挿入しやすくなるため、粘膜全体をくまなく観察でき、より質の高い検査が可能です。
以下に、当クリニックの大腸カメラ検査の特徴をご紹介します。ぜひご覧ください。
- 日本消化器内視鏡学会専門医が検査を担当します。
- 鎮静剤を使用し、苦痛の少ない内視鏡検査を行います。
- オリンパス社製の高性能内視鏡システムを導入しています。
- 大型高精細液晶モニターを使用し、精細な検査と適切な診断を行います。
- 早朝・午前中の大腸カメラ検査が可能です。
- 土曜・日曜にも大腸カメラ検査を実施しています。
- 胃カメラと大腸カメラを同日に受けることができます。
- 大腸ポリープの日帰り切除が可能です。
- 女性医師による大腸カメラ検査も対応しています。
検査をご希望の方へ
大腸カメラ検査をご希望の方は、まず外来受診をおねがいしております。安全に検査を行うため、外来診察時に検査の必要性やリスクについて、医師がしっかりと判断させていただきます。
また、当クリニックではインターネット予約システム(WEB予約)を導入しています。当クリニックのホームページからWEB予約をご利用いただけます。操作方法がわからない場合やお困りの際は、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
患者さんに安心して診療を受けていただけるよう努めております。どうぞお気軽にご相談ください。
便潜血陽性、血便、下血で疑われる病気
大腸がん
大腸がんは初期には自覚症状がほとんどないため、病気が進行した状態で発見されることもあります。近年では食生活の欧米化により、大腸がん患者数は増加傾向にあると言われています。大腸がんは大腸カメラで発見できるため、下痢や便秘、血便などの症状に心当たりのある方は、早めに大腸カメラ検査の受診をおすすめします。
大腸ポリープ
 大腸ポリープは、大腸の粘膜が増殖して隆起してくるものです。その形や大きさはさまざまで、1mmほどの小さなものから数cmに達するものまであります。
大腸ポリープは、大腸の粘膜が増殖して隆起してくるものです。その形や大きさはさまざまで、1mmほどの小さなものから数cmに達するものまであります。
ポリープには、非腫瘍性と腫瘍性の2種類があり、腫瘍性ポリープは切除の対象となります。腫瘍性ポリープには、大腸ポリープの80%以上を占めるといわれる腺腫や、いわゆるがんが含まれます。
大腸ポリープが腫瘍性か非腫瘍性かを診断するには、大腸カメラ検査が必要です。早期発見と適切な治療のため、検査を受けることをおすすめします。
炎症性腸疾患
炎症性腸疾患(IBD:Inflammatory Bowel Disease)とは、主に腸管に原因不明の炎症を引き起こす慢性の疾患の総称です。代表的な疾患として「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」があります。再燃と寛解を繰り返す病気で、いずれも国の難病指定を受けています。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、大腸粘膜に炎症が起こる原因不明の慢性の炎症性腸疾患です。
本邦では年々増加傾向にあり、20~30歳代に多い傾向がありますが、若年者から高齢者まで発症します。多くは直腸から連続性に口側(奥側)に広がっていき、炎症の範囲によって、直腸型、左側結腸炎型、全結腸炎型に分類されます。
腹痛、下痢、粘血便などの症状が見られ、長期にわたって大腸の粘膜が炎症を繰り返すと、そこに大腸がんが発生することもあります。
クローン病
クローン病は、口腔内から肛門にいたるまでの消化管のどの部位にも炎症を引き起こします。主として若年者にみられ、腹痛や下痢、血便、体重減少などが生じます。
病気が進行すると、腸の狭窄(狭くなる)や膿瘍(腸の外側に膿がたまる)、瘻こう(他の腸や臓器にトンネルが出来、交通する)を合併することもあります。
胃潰瘍
胃の粘膜が傷つき、炎症が生じる病気です。
主な原因はピロリ菌感染で、他には過度な飲酒、ストレス、鎮痛薬の長期投与などが挙げられます。
症状として、みぞおちや背中の痛み、胃もたれ、腹部の張り、吐き気などがあります。場合によっては潰瘍から出血し、吐血や黒色便が現れることがあります。
内視鏡検査を用いた診断と、ピロリ菌除菌や薬物療法などが必要となります。
十二指腸潰瘍
胃の奥にある十二指腸の入口(十二指腸球部)に多く見られます。
十二指腸の壁は胃の壁よりも薄いため、穿孔(穴が空く)を起こしやすい傾向があります。胃潰瘍と同様に、ピロリ菌の感染率は高いといわれています。内視鏡検査を用いた診断と、ピロリ菌除菌や薬物療法などが必要となります。
食道がん
食道がんは、食道の粘膜表面に発生するがんです。発生する部位は食道のどの部分にも及びますが、特に食道の中央付近に発生するケースが多く、全体の約半数を占めると言われています。また、食道内に同時に複数のがんが発生することもあります。
初期の食道がんはほとんどの場合、自覚症状がありません。そのため、進行するまで気づかれないことが少なくありません。がんが進行すると、飲食時に胸に不快感を感じる、喉に食べ物や飲み物が詰まったような感覚がある、体重減少、胸痛や背中の痛み、咳、声のかすれなどの症状が現れることがあります。
早期発見が重要な病気ですので、上記のような症状が続く場合や気になる点がある方は、ぜひ一度ご相談ください。当クリニックでは、精密検査や早期診断に力を入れています。お気軽にお問い合わせください。
胃がん
近年の胃カメラ検査の性能向上により、無症状の早期胃がんの発見が可能となっています。進行すると吐き気や腹痛、出血による黒色便や貧血などの症状が出現します。
早期がんであれば、内視鏡的治療や外科切除によって完治が期待できます。早期発見が重要な病気ですので、上記のような症状が続く場合や気になる点がある方は、お気軽にお問い合わせください。