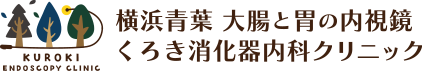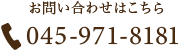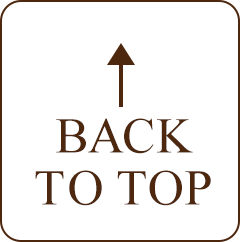おならとは
おならは、主に2つの要因で発生します。1つは口から飲み込んだ空気、もう1つは体内で食べ物が消化される際に発生するガスです。これらのガスの大部分は体内で吸収され、呼気として排出されますが、一部は吸収しきれずにお尻から排出されます。
おならが多くなる主な原因として、無意識に空気を過剰に飲み込む習慣(呑気症)があります。早食いやガム・飴の過剰摂取などが代表的です。また、腸内細菌叢のバランスが崩れることでも、おならが増加する傾向にあります。
健康的なおならの頻度
健康な成人では、1日平均10数回程度のおならが一般的とされています。ただし、食生活の違いやストレス、睡眠状態などにより個人差が大きいため、この回数のみで健康状態を判断することは適切ではありません。
お腹の張りや便通異常(便秘・下痢)を伴う場合は、重大な疾患が潜んでいる可能性があります。日常生活に支障をきたす場合は、消化器内科の受診をお勧めいたします。
おならのにおいの原因
 おならの約70%は、食事や呼吸で取り込んだ空気です。これに加えて、腸内細菌による食物分解で発生するガスが混ざり、おならとなります。
おならの約70%は、食事や呼吸で取り込んだ空気です。これに加えて、腸内細菌による食物分解で発生するガスが混ざり、おならとなります。
おならの成分の大半は無臭ですが、腸内細菌が食物を分解する過程で発生するガスに特有のにおいがあります。体調不良時や過食時には、このにおいが強くなる傾向があります。
おならのにおいはゆで卵のにおい?
おならの不快なにおい(ゆで卵様・硫黄様)の主成分は硫化水素です。人間の鼻は極めて微量の硫化水素でも感知できるため、わずかな増加でも不快に感じられます。
この硫化水素は、大腸内の特定の細菌(硫化水素産生菌)の活動により生成されます。なお、大腸がんの存在により腸内細菌叢が乱れ、おならのにおいが強くなることもあるため、注意が必要です。
おならがよく出る原因
消化器疾患が原因
慢性胃炎
約80%がピロリ菌の感染によるもので、ピロリ菌は胃の粘膜に慢性の炎症を引き起こします。
胃痛、げっぷ、吐き気、胸焼け、腹部膨満感などの症状に加え、おならも増えます。放置すると胃潰瘍に進行する恐れがあります。
過敏性腸症候群
検査をしても異常が見つからないのに、慢性的下痢、便秘、それに伴う腹痛が生じる病気です。不安や緊張などの心理的ストレス、気候の変化などの環境的ストレス、過労などの身体的ストレスが原因で起こると考えられています。また、過剰なガスがたまりお腹が張る症状もあります。おならを我慢するとにおいが漏れるのではないかと心配になり、公共の場にでることを避けるようになる方もいらっしゃいます。
大腸がん
大腸がんの初期には自覚症状がほとんどありませんが、進行すると、便秘と下痢を交互に繰り返す、便が細くなる、腹部膨満感などが生じてきます。腸が狭くなると、頑固な便秘や弱いおならが頻繁に出るようになります。
生活習慣が原因
悪玉菌が増加する食事(動物性食品の過剰摂取)
 肉には脂肪やタンパク質が多く含まれており、過剰摂取するとおならが臭くなる傾向があります。
肉には脂肪やタンパク質が多く含まれており、過剰摂取するとおならが臭くなる傾向があります。
肉や卵などの動物性食品を摂取すると腸内の悪玉菌が増殖し、悪臭を伴うガスが発生しやすくなります。特に焼肉を食べた後にはおならが増加することが特徴的です。また、脂肪分の多い食品は消化に時間を要し、腸内での発酵が進みやすくなります。
豊富な食物繊維
豆類やイモ類などに含まれる食物繊維は、腸内に長く留まり、消化に時間がかかります。その過程で酵素による分解が進み、ガスが増加します。頻繁なおならでお困りの方は、食物繊維の過剰摂取がないか、食生活の見直しをお勧めします。ただし、食物繊維は腸内環境の健康維持に不可欠な栄養素です。食物繊維を含む食品は、体調を観察しながら徐々に摂取量を増やしていくことが望ましいでしょう。
炭酸飲料
ビールや炭酸飲料などは、二酸化炭素と水に分解されるため、おならの増加につながります。
喫煙
喫煙をやめると食物の分解が活発化し、腸内細菌が増殖する傾向があります。特に、腸内に老廃物が長時間滞留している場合や禁煙期間中は、おならのにおいが強くなりやすい特徴があります。
ストレスや睡眠不足による自律神経の乱れ
ストレスや睡眠不足により自律神経が乱れ、特に副交感神経がうまく働かなくなると、胃腸の働きが鈍くなり、消化が遅延します。その結果、ガスが発生しやすくなります。おならは生理的な現象であり、完全に防ぐことはできませんが、腸内にガスが蓄積してストレスとなることは予防可能です。
おならの予防
きついにおいの原因となる食べ物に注意
 肉類、ネギ類、にんにくなどの過剰摂取は、大腸での分解過程でにおいの強いおならの原因となります。また、ウェルシュ菌などの悪玉菌の活動も強いにおいを発生させます。ヨーグルトに含まれるビフィズス菌などの善玉菌を積極的に摂取し、腸内環境を整えることが重要です。
肉類、ネギ類、にんにくなどの過剰摂取は、大腸での分解過程でにおいの強いおならの原因となります。また、ウェルシュ菌などの悪玉菌の活動も強いにおいを発生させます。ヨーグルトに含まれるビフィズス菌などの善玉菌を積極的に摂取し、腸内環境を整えることが重要です。
便秘予防のための生活習慣改善
便秘を防ぐことは、お腹の張りやおならの予防にも繋がります。
そのため、以下の点に注意して生活習慣の改善を図りましょう。
- おならを我慢せず適切に排出する
- 便意を感じたら速やかに排泄する
- 十分な水分を摂取する
- 適切な食物繊維を摂取する
- 定期的な運動を心がける
自宅やトイレなどの適切な場所では、おならを我慢せず排出することで、お腹の張りや便秘を予防できます。ウォーキング、足踏み、ヨガなどの運動はガスの排出を促進します。
じゃがいもや豆類の摂取は便通改善に効果的です。また、オリゴ糖には便秘改善効果があります。オリゴ糖の摂取後、一時的な腹部膨満感やおならの増加が見られますが、これはオリゴ糖が腸内で代謝され、炭酸ガスが生成されるためです。このガスは有害菌が産生するメタンガスと異なり、においはありません。
リフレッシュしてストレス解消
ストレスは胃腸機能に大きな影響を与え、過敏性腸症候群の原因となることがあります。
周囲の目を気にしておならを我慢する方は、お腹の張りやにおいへの不安が強くなりがちです。心身のリフレッシュのため、リラックスできる時間や空間を確保することが大切です。旅行、休日のショッピング、スポーツなどの活動もお勧めです。
おならを我慢することは
体に悪い?
 おならを我慢すると腸内にガスがたまり、腹痛の原因になり、腸の働きが悪くなることで便秘に陥りやすくなります。
おならを我慢すると腸内にガスがたまり、腹痛の原因になり、腸の働きが悪くなることで便秘に陥りやすくなります。
また、我慢したおならのガスが腸から血液に溶け込んで全身に運ばれ、皮膚や呼気から排出されることになります。そのため、長くおならを我慢すると、体臭や口臭が強くなることもあります。
おならは我慢せず、腸内環境を整えることで、においのするガスや量を減らすことを目指しましょう。