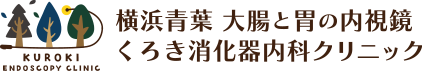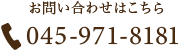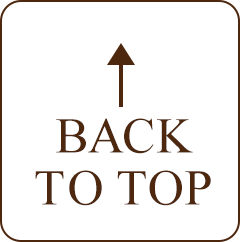機能性ディスペプシアとは
 機能性ディスペプシアとは、胃カメラ検査などでは異常が見つからないものの、胃痛や胃もたれなどの症状が続く病気です。機能性胃腸症とも呼ばれます。
機能性ディスペプシアとは、胃カメラ検査などでは異常が見つからないものの、胃痛や胃もたれなどの症状が続く病気です。機能性胃腸症とも呼ばれます。
そもそも、逆流性食道炎や胃炎が胃カメラ検査で発見された場合でも、患者さんが症状を訴えているとは限りませんし、逆に症状があっても検査で異常が見つからないこともあります。そのため、胃カメラ検査で所見があってもなくても、症状を説明できる異常が見つからない状態を「機能性ディスペプシア」と診断されることがあります。
機能性ディスペプシアの症状
 患者さんによっては、食後のお腹の張りや胃もたれ、みぞおちのあたりが焼け付く感じがする、胃が存在感を主張している感じがするといった症状を訴える方もいらっしゃいます。また、げっぷや胸焼けが起こることもあります。このように、さまざまな症状が起こる上に、良くなったり悪くなったりを何度も繰り返します。季節によって痛むこともあれば、ストレスがかかると症状が出ることもあります。
患者さんによっては、食後のお腹の張りや胃もたれ、みぞおちのあたりが焼け付く感じがする、胃が存在感を主張している感じがするといった症状を訴える方もいらっしゃいます。また、げっぷや胸焼けが起こることもあります。このように、さまざまな症状が起こる上に、良くなったり悪くなったりを何度も繰り返します。季節によって痛むこともあれば、ストレスがかかると症状が出ることもあります。
機能性ディスペプシアの原因
機能性ディスペプシアの原因を特定するのは容易ではありません。さまざまな原因が複合的に関わって起こると考えるのが一般的です。
胃腸の動きの問題・知覚過敏
胃や十二指腸の運動のリズムが乱れ、食事をうまく送り出すことが出来ないと痛みが起こる場合があります。また、胃は拡張と収縮を繰り返していますが、このような通常の運動でも痛みを敏感に感じる場合があると考えられています。
胃液の過分泌
胃液は消化に必要なものですが、過剰に分泌されると胃の粘膜を刺激し、症状を引き起こす可能性があります。
ストレス
ストレスによって胃や腸が過敏になり、痛みを感じることがあります。
感染性胃腸炎
機能性ディスペプシアは、感染性胃腸炎を発症した後、何らかの理由で引き起こされることがあります。
生活習慣
飲酒、喫煙、不眠などといった生活習慣が原因となって、機能性ディスペプシアが引き起こされることがあります。
機能性ディスペプシアの検査
 一般的な症状として、胃の不快感や痛み、胸焼け、吐き気などがあり、これらの症状が長く続くようであれば、胃カメラ検査で炎症や潰瘍、がんなどの症状を伴う病気を否定する必要があります。また、血液検査やピロリ菌の検査で異常がないことも確認することが推奨されます。機能性ディスペプシアと診断された場合は、ストレスを軽減するなど生活習慣を改善することで、症状が改善される可能性があります。
一般的な症状として、胃の不快感や痛み、胸焼け、吐き気などがあり、これらの症状が長く続くようであれば、胃カメラ検査で炎症や潰瘍、がんなどの症状を伴う病気を否定する必要があります。また、血液検査やピロリ菌の検査で異常がないことも確認することが推奨されます。機能性ディスペプシアと診断された場合は、ストレスを軽減するなど生活習慣を改善することで、症状が改善される可能性があります。
機能性ディスペプシアの治療
つらい症状があっても、まず「重い病気ではない」ということを認識することが治療の第一歩です。来院された多くの方が、胃カメラ検査で異常がないことを確認し、病気の説明をさせていただくと、自然と気持ちが楽になるようです。ただ、それでも症状が残る場合は生活習慣の見直し(刺激の強い食品や脂肪分の多い食事、アルコールやカフェインを摂り過ぎない、また夜更かしや無理をしないなど、ストレスを避け睡眠や休息を十分に取るなど)やお薬(胃酸を抑える、胃の運動を整えるお薬や不安を取り除くお薬など)を用います。すぐに改善が見られなくても、ご自身に合った治療を見つけていきましょう。
機能性ディスペプシアを
軽減させるために
機能性ディスペプシアは、3つの異常、すなわち胃の膨らみ不良、胃の運動機能の異常、胃の知覚過敏(胃酸に対する感受性亢進)によって症状が生じるとされています。これらの3つの異常を改善し、かつストレスに対処するアプローチは、症状の緩和に役立ちます。
胃の膨らみ不良・胃の運動機能異常・胃の知覚過敏に対するアプローチ
胃の中に食べ物が長く留まるほど、不快な胃の症状は悪化します。
そうならないためには、胃で消化されにくい食べ物を避けることが効果的です。
食べ物が胃の中に留まる時間は、脂肪>炭水化物>タンパク質と脂肪が長くなります。
天ぷらやステーキなど脂肪分の多い食べ物は胃で消化されにくく、消化不良や吐き気などの症状を悪化させることがあります。
症状がひどい場合は、胃の運動を改善するために、必要に応じて胃腸運動改善薬や知覚過敏に対しては胃酸の分泌を抑えるお薬を適宜考えていきます。
ストレスに対するアプローチ
機能性ディスペプシアは、ストレスなどによる自律神経の乱れも症状悪化の一因と考えられています。
また、機能性ディスペプシアでは、症状そのものがストレスとなり、さらに症状が悪化するという悪循環に陥ることもあります。休みの日にはのんびりしたり、好きなことを楽しんだりしてストレスを解消し、根本的な原因を取り除くことが重要です。