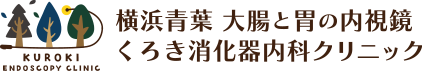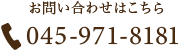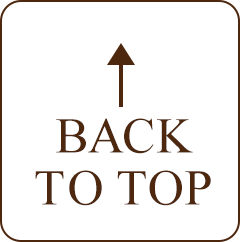- 大腸(結腸・直腸)について
- 大腸がんとは
- 大腸がんの症状~大腸がんはどうやって気づく?~
- 大腸がんの便はどんな特徴がある?
- 大腸がんの原因
- 大腸がんの検査
- 大腸がんの治療
- 大腸がんで亡くなる方が多い理由
大腸(結腸・直腸)について
 大腸は食物の最終通路です。小腸から続く、長さは1.5~2mほどの管状の臓器で、結腸(盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸)と直腸に分けられます。
大腸は食物の最終通路です。小腸から続く、長さは1.5~2mほどの管状の臓器で、結腸(盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸)と直腸に分けられます。
さらに直腸は直腸S状部と腹膜反転部によって上部直腸と下部直腸に分けられます。大腸の壁は内側から粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜の5層に分かれています。
大腸の主な働きは水分の吸収です。大腸には栄養素を消化吸収する働きはほぼありません。小腸で消化吸収された内容物は、大腸でさらに水分を吸収されながら肛門に移動し、徐々に固形の便になります。大腸での水分吸収が不十分だと、軟便や下痢の原因になります。
大腸がんとは
大腸がんは大腸(結腸と直腸)に発生するがんです。その発生経路には、腺腫と呼ばれる良性のポリープから発生するものと、正常な粘膜から直接発生するものの2種類があります。
大腸がんは、S状結腸と直腸に発生しやすいことが知られています。
大腸がんは大腸の粘膜に発生し、徐々にその後、壁の外側へと広がり、がん細胞が腹腔全体に散らばる腹膜播種を引き起こすことがあります。また、大腸壁を流れるリンパ液によって、リンパ節への転移や、血流を介して肝臓や肺など他の臓器に転移することもあります。なお、肺や肝臓に見つかった腫瘤が、大腸がんの転移の発見契機となることもあります。
大腸がんの症状・症状の現れ方
~大腸がんはどうやって気づく?~
 早期の大腸がんには自覚症状がほとんどありませんが、進行するにつれてさまざまな症状が現れることがあります。典型的な症状としては、便に血が混ざる(血便)、排便習慣の変化(便秘や下痢)、便が細くなる、排便が終わってもスッキリしない(残便感)、貧血、腹痛、嘔吐などがあります。
早期の大腸がんには自覚症状がほとんどありませんが、進行するにつれてさまざまな症状が現れることがあります。典型的な症状としては、便に血が混ざる(血便)、排便習慣の変化(便秘や下痢)、便が細くなる、排便が終わってもスッキリしない(残便感)、貧血、腹痛、嘔吐などがあります。
症状は大腸がんの発生部位によって異なります。S状結腸や直腸にがんができた場合、硬い便が通過する部位であるため、便が細くなる、腹痛や嘔吐が起こる、便に血が混ざるなどの症状が現れやすくなります。一方、盲腸、上行結腸、横行結腸に発生した大腸がんでは、進行しても目立った腹部症状が出ないことが特徴です。このような場合、貧血や腹部のしこりなどの症状から発見されることがあります。
大腸がんの便は
どんな特徴がある?
血便
血液が混じった便を血便と言います。大腸がんが進行すると腸内で出血が起こり、血便が見られることがあります。大腸の前半部分(盲腸、上行結腸、横行結腸)での出血では便に赤黒い血液が混じります。一方、後半部分(下行結腸、S状結腸、直腸)からの出血では真っ赤な血液が付着する傾向があります。ただし、血便は痔、大腸ポリープ、大腸憩室出血、虚血性腸炎などでも起こるため、大腸がんに特有の症状ではありません。血便が見られた場合は、早めに医療機関を受診し、原因を調べることが重要です。
急な便秘・下痢を繰り返す
がんが大きくなると、大腸の内腔が狭くなり、一定の間隔で繰り返す下痢や便秘などの排便異常が起こりやすくなります。さらにがんが大きくなると、便が排出されにくくなり、腹痛や嘔吐などの症状を引き起こすこともあります。なお、便通異常は、大腸がんの他にも、潰瘍性大腸炎や、クローン病などの大腸の疾患、甲状腺機能異常、糖尿病、月経周期や妊娠中のホルモン変化によっても引き起こされます。また、薬の副作用で便秘や下痢になることもあります。
便の性質が変わる
S状結腸や直腸がんが大きくなり内腔が狭くなると、便が細くなったり、コロコロと小さい塊状になったりします。また、排便後も腸内に便が残っているような残便感を覚えることもあります。
ただし、コロコロとした小さい塊状の便は便秘の場合にも、残便感は痔の場合にも見られる症状です。
大腸がんの原因
大腸がんのリスク要因として、生活習慣に関連するものには、運動不足、野菜や果物の摂取不足、肥満、飲酒などの生活習慣が挙げられます。
過去20年間で大腸がんによる死亡者数は1.5倍に増加しており、その背景には生活習慣の欧米化(高脂肪・低食物繊維の食事)が関与していると考えられています。
また、大腸がんの家族歴がある場合や、潰瘍性大腸炎を長期間患っている場合も、大腸がんのリスクが高くなります。
大腸がんの検査
便潜血検査
本邦では、自覚症状のない大腸がんを発見するために、便潜血検査が対策型検診として推奨されており、40歳以上を対象に市区町村単位で行われています。
便潜血検査は、便の中の血液反応を調べることで出血の有無を確認する検査です。検査には2日間の便のサンプルを採取します。主に免疫法(便に含まれるヒトヘモグロビン(赤血球のタンパク質)を検出する検査法)を採用しており、基本的に食事制限は必要ありません。
検査の結果、精密検査が必要と判断された場合は、大腸がんの早期発見のため、大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)を受けることをお勧めします。
大腸カメラ検査
 大腸カメラ検査は(大腸内視鏡検査)は、肛門から専用の細長い内視鏡を挿入し、大腸内部を詳しく観察する検査です。大腸がんやポリープ、炎症性腸疾患などの早期発見・診断に最も信頼性の高い検査方法です。
大腸カメラ検査は(大腸内視鏡検査)は、肛門から専用の細長い内視鏡を挿入し、大腸内部を詳しく観察する検査です。大腸がんやポリープ、炎症性腸疾患などの早期発見・診断に最も信頼性の高い検査方法です。
検査のメリット
- 大腸内部を直接観察できるため、微細な病変も発見可能
- 発見されたポリープや早期がんはその場で切除が可能
大腸がんは早期に発見できれば、90%以上が完全に治癒すると言われています。精密検査が必要と判定された場合は、大腸カメラ検査を受けることをお勧めします。
当クリニックでは、患者さんの不安や苦痛を軽減するため、希望される方には鎮静剤を使用した「苦痛の少ない検査」を実施しております。検査に対する不安や疑問点がございましたら、お気軽に医師やスタッフにご相談ください。
大腸がんの治療
がんの進行度によって、治療方針は異なります。がんが粘膜内や粘膜下層に浅く留まり、リンパ節や他の臓器への転移がない場合は、大腸カメラによる内視鏡的切除が適応となります。一方、がんが壁の深い層まで達している場合や、リンパ節転移が認められる場合は、外科的治療(手術)が適応となります。また、他の臓器への転移が認められる場合は、化学療法(抗がん剤治療)との併用を検討します。
がんの進行度には個人差がありますが、大腸がんは根治切除ができれば長期生存が期待できます。近年は化学療法の治療成績も向上しており、以前は切除が困難と判断された症例でも、化学療法による腫瘍縮小効果により切除が可能となったケースが増えています。
大腸がんで亡くなる方が
多い理由
 国立がん研究センターの報告(2022年)によると、大腸がんによる死亡者数は、男性が2位、女性では1位となっています。
国立がん研究センターの報告(2022年)によると、大腸がんによる死亡者数は、男性が2位、女性では1位となっています。
この統計が示すように、大腸がんは日本人のがんによる死因の多くを占めています。
その背景には、食事の欧米化や高齢化による罹患数の増加があります。さらに、他のがん検診と比較して、便潜血検査で陽性となった方の精密検査(大腸カメラ検査)受診率が低いことも要因として挙げられます。
大腸がんは、早期発見・早期治療を行えば、90%以上の確率で根治が望めるとされています。便潜血検査で陽性と判定された場合は、必ず大腸カメラ検査を受けることをお勧めします。